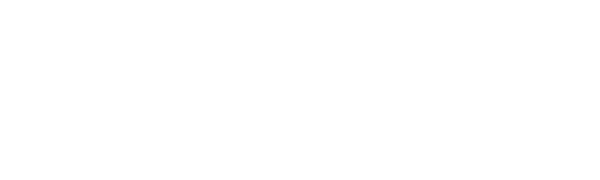森の小さな日用品店
ヒカセン(ミコッテ♀)の実家の店と客のおはなし。
・弓術士クエスト微ネタバレ
・ヒカセンは出ない。兄貴は出る。
「すまん、ちょっといいか」
店主に向かって語気鋭くまくし立てる爺の背後から俺は声をかけた。
先程から激しい怒号を店主に浴びせているのはこの店の常連の爺だ。と、言っても客の俺から見てもそんなにいい客ではないと思う。大して買い物をしないくせに長く居座って長話をするか、それこそこんなふうに少しでも自分の意に沿わないと大声で怒鳴り散らしている。俺がこの店に一杯引っ掛けに行くと、三日のうち一日くらいは出くわす。出くわすと今日は運がないと落胆する、そんな爺である。
そして、怒号を浴びせられているのはここの店主、正確には店主の代わりに店番をしているミコッテ族の青年だ。まあ彼も彼で良い店主とは言えない。商品の場所を知らない、金の計算はおぼつかない。おまけに愛想も悪い。正直爺が機嫌を損ねるのも理解できる。
しかし、その状態を放置して酒を飲んでいられるほど、俺も神経が太いわけじゃない。だから助け舟を出そうと思ったのだ。
「右の棚。その、豆袋の置いてある所の隣にないか?」
いつもそのへんから、爺の所望する商品を女将が取り出している覚えがあった。そのことを伝えると、青年は面食らいながら棚に近づき、すぐ目当ての品を見つけ出して引っ張りだした。
「ったく、お前の家の店だろうが。商品の場所くらい覚えろよ」
爺は悪態をつきながらギル硬貨をカウンターに叩きつけ、青年の手から品物をひったくると肩を怒らせながら店を出ていった。良かった。そのままうだうだと説教でもされたら今夜の晩酌が台無しになるところだった。俺はやれやれとため息をつく。
「あ、あの……助かった」
当の店主からもごもごとした声で礼を投げかけられた。肩をすくめながら俺はこう返す。「気にするな。ぎゃあぎゃあやかましくて仕方がなかったからな」
ちらりと青年の顔をうかがい見る。ここ最近本来の店主、女将の代わりにいるのがこの青年だ。女将の息子である彼だが黒髪黒肌のムーンキーパー然とした女将とは違い、退紅色の髪に褐色の肌、瞳孔は針のように細くーーつまり見るからにサンシーカーの特徴が色濃く出ている。
そう言えば、息子の父親はどこぞのサンシーカーの一族のヌンだがなんだかと女将があけすけに話をしていたな、とシードルに口をつけながら思い出す。子供の頃から体が弱く、独り立ちせず家に残ってる息子。娘と違って根暗だし体力もなくて……だったか?それが彼なのだろう。
と、カウンターに座る俺の目の前にエールの瓶がとん、と置かれた。見上げると青年が相変わらず仏頂面で、しかし意外な事を言った。
「お礼。一本サービス」
こいつ、そんな気回しができたのか。それがその時の正直な感想だった。
***
俺もそこまで愛想がいいわけじゃない。人と騒ぐのも好きじゃないし、ひとりでいるのが好きだ。要は似た者同士だったわけで、その後店で顔を合わせる回数が増えると、俺は彼にとってそこそこ顔なじみの客になった。
「いつものでいいか」
青年は店に入ってきた俺の顔を見るなり、シードルの瓶を取り出した。あれから商品の場所も覚え、金勘定もだいぶ早くなった。愛想は、相変わらずだが。
「ああ。それと煙草も頼む」
俺がそう言うと彼は手際よく煙草を包み、紙袋に入れてカウンターに置いてくれる。
「パワが捕まったって話聞いたか?」
煙草に火をつけながら俺が話しかけると、彼はうなずいた。
「ああ。神勇隊のお縄にかかったんだったか?」
「どうも実際は弓術士ギルドの連中と冒険者が仕留めたらしい」
青年もいつの間にかエールの蓋を開けている。冒険者ね、と呟くと彼は瓶をあおった。
「案外またお前の妹だったりしてな」
「はは、それはねーだろ」
青年は薄ら笑いを浮かべている。
「あいつ昔から弓やら槍やらはからっきしだったんだよ。狩りも石握って殴ってたぐらいだ」
こうして話題に出てくるのは冒険者として頭角を現しているらしい彼の妹、女将の娘ということにもなるが、その子の話だ。女将に瓜ふたつの黒髪黒肌、正しくムーンキーパーの娘というのは彼の言葉だ。
「俺と違ってな」
初めてその子の話をした時、彼は自嘲気味にそう付け加えた。サンシーカーの血が色濃く出てしまったせいでムーンキーパーの生活や環境に馴染めず「子供の頃から身体が弱く体力もない」……根暗は血とは関係ないのでどうしようもないだろう。
そして、こうした彼の妹の噂について話すごとに、俺はある確信を得た。青年は親と折り合いが悪く、しかし妹との関係は良好。しかし、それを知ったところで、まあだからなんだという話である。
ひとつの話題が終わると、俺は静かに晩酌を再開し、青年は酒を片手に本や妹からの手紙を読む。しばらくしてまたひとつ話題に言葉をかわすこともあるし、そのまま閉店時間まで静かに過ごすこともある。俺はこの空気がなんとなくだが好きだった。
***
彼の妹がますます活躍し、「英雄」などと持て囃されるようになると、店には里帰りしてきた「英雄」に会えやしないか、せめて「英雄」の家族に会ってみたいなどと言うようなかぶれた一見の客が増えた。
最近は、夜「閉店」の木札が扉に掲げられる頃に訪れると、青年がこっそり客を招き入れる。地元の連中はそうやって入店し、買い物をしたり酒の飲めるカウンターで本当の閉店時間まで過ごすようになった。
「割に合わない」
そう零すと、いつものように蓋を開けたシードルの瓶と、紙袋に入れた煙草を俺の前に置いた。
「……お疲れ」
俺としてはそうとしか言えない。もうこの頃には、女将はほとんど顔を出さなくなっていた。いや、正確にはだいぶ前から息子に店を押し付けて、自分は娘に買ってもらった海都の家で男としけこんでいるとの事だ。例の面倒な爺も様変わりした店の雰囲気を嫌ってか、すっかり寄り付かなくなっていた。
「あのジジイはもともと母親が目当てだからな。そりゃそうだろうよ」
ある時、そのことを指摘すると青年はエールを煽りながらそう答えた。「けど、今となってはジジイのお守りのほうがマシだった」
もともと地元の人間相手に食料やら日用品やらを売っていた店だ。そういう人間に来てもらわなければ商売上がったりだろうに、今は「英雄」目当ての一見客がひっきりなしにやってくる。日中はそんな奴ら相手に酒やら菓子やらを売り込んで話し相手になっているのだ。この人見知りで根暗の青年が。
「妹に会いたいというのはまだわかるが……俺と話がしたいと言うのは何なんだ」
「英雄殿が子供だった頃の話でも聞きたいんだろ」
「俺の年齢やらなんやらを聞くのは違うだろ」
俺は思わず苦笑いした。性格は陰気だが彼の顔は端正な方だ。そっち狙いで訪れる女性がいてもおかしくないと、俺は正直思った。
「なあ」
しばらく黙ってお互い酒を口に運んでいたが、そのうち彼が俺の顔色を伺いながら切り出した。
「この店閉めようと思うんだが、そうなるとお前、困るか?」
「……………」
言葉に詰まった。正直、困らない。
そうなのだ。このミコッテの店が無くなった所で、買い付け先や晩酌の場はいくらでもある。住まいよりは少し遠くなって狩りの帰りに寄るにはいささか不便なくらいなものだ。
俺が答えあぐねていると、彼の耳がしお、と垂れた。思うに、ここまで感情豊かな反応は初めてだ。
「なんていうか、俺に気遣いはしなくていい。率直な意見を聞きたい」
「そうか」
俺はひと呼吸おくと、考えたとおりにとおりに話した。
「そんなもんだ。お前には悪いが」
「いや…………正直肩の荷が下りたよ」
彼はそう言うと、手に持っていたエールを一気に飲み干した。
「店がこうなって、妹が責任を感じてしまったみたいでな。あまりひどいなら店を畳んで、自分のリテイナー?てのをやらないか、と言ってくれてる」
「リテイナー?」
「冒険者の持ち物を管理したり、アイテム売買の代行をしたり、だそうだ」
まあそれなら体力なくてもできそうだからな、と青年は二本目のエールの瓶を開ける。
「いいじゃないか。……あ、でも女将さんは」
「問題ないだろ。あの人はもうこの店がどうなろうと気にしない」
彼はそう言うと薄ら笑いを浮かべた。
「妹も、そう思ったから言ってくれたんだろうしな」
***
昼休憩をしようと、俺はそのあたりの手頃な岩に腰をかけたていた。飯を食う前に、と馴染みの煙草に火を付ける。あのミコッテの店よりも住まいから遠い、しかし同じ頻度で通っていた別の店で買ったものだ。
あの夜から三日後、いつものように夜店を訪れると、扉には閉店の知らせが貼られていた。
ーー店主都合により閉店しました。長らくのご愛顧ありがとうございました。
何のひねりもないありふれた文言だった。中を覗くと棚も商品もなくなり、きれいに掃除されてがらんとしていた。
しかしおもむろに扉が開くと彼が顔を出してーーなどということもなく、あの夜を境に関係は途切れた。もしかしたら閉店までの間、いつもの酒と煙草を用意して待っていたのかもしれないが、俺はなんとなく行く気分にならず、それっきりになってしまった。
俺は煙草を吸いながら考える。彼はもう妹の待つウルダハに発ったのだろうか。それともまだ黒衣森にいて、出立の準備をしているのだろうか。なんにせよ知るすべはもう無い。
「所詮は店主と客の関係、だからな」
俺は大きく煙草の煙を吐き出した。通っている店が無くなった。煙草の購入先が変わった。好物のシードルは買えなくなった。ーーこうした大小の変化はあれど、大筋は変わらず、日常は続くのだ。