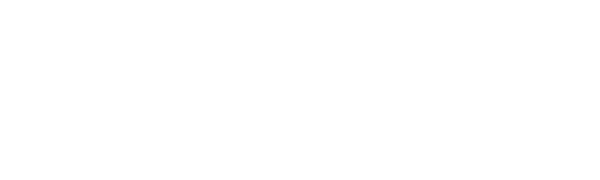海都の男
とある商人の男が、冒険者居住区にあるアパルトメント「トップマスト」の一室を譲り受ける事になったのは、とある冒険者からの計らいであった。
そのように説明するとさも好意的な事からのように聞こえるが、実際の所譲りたかった相手は冒険者の家族であり、冒険者ではないその家族のために冒険者ギルドに籍だけは残っていたこの男に便宜上「譲渡する」形を取っただけだ。男は家族の恋人であった。
約束の日、冒険者は訪ねてきた男を笑顔で迎え入れたが、肝心の家族の姿が無いことを認めると、あからさまに失望した顔をした。
「……そんな顔しないでよ。ニケさんはどうしても今日来れないって」
「そう」
素っ気なく返事をすると、冒険者は男が入室できるよう扉の横に体をずらした。
「とりあえず入れば?」
「おじゃまします……」
今日から自分の居室の筈なのだが、その男、ア・ムジ・ティアは年頃の娘の自室に入るかのように遠慮がちな面持ちで入室した。
部屋は以前訪問した時とは全く違う様相になっていた。オサードブルーの漆喰で塗られていた壁は白木の板張りに取り替えられ、部屋の一角を占拠していた魔導書や怪しい遺物は取り払われて代わりに同じ場所には素朴な棚が造り付けられている。その横には使い勝手の良さそうな織り機が置かれていた。
なるほどこれは全て恋人の趣味だ、と男は早々に悟る。この織り機も裁縫士として生計を立ててきた女の仕事道具である。ア・ムジは、母親のために新居を設えた親孝行の娘に目を細めた。
「……見違えたよ。これシオンちゃんが手配したの?」
「他に誰がやんのよ」
譲渡者の冒険者であり男の恋人の娘たるシオンの反応は大変に酷薄であった。ア・ムジに対してこの娘はいつもそうだ。無視などはしないが言葉も向ける表情も刺々しい。しかしながら、ア・ムジがめげずに会話を試みるのもいつもの事だ。
「内装や家具も作ってくれたのかな? 職人としても腕利きでしょう?」
「ほとんど買ったものだけど」
とりつく島もないとはこういう事か。ア・ムジはため息をついて苦笑した。
***
もはや知らない者はいないであろう暁の英雄。その人となりは「人懐っこく、誰に対しても親切で、朗らか」……なのだが、この男に対してだけは違う。それはそうだ。父親とは違う母親の恋人。良好な関係になる方が珍しい。彼女の両親が夫婦関係のままであれば尚の事。……そう思っていた。
「別にそこは問題じゃない」
以前、自分に対して冷たい理由を推測し、「気持ちは分かるよ」などと諂ったア・ムジにシオンはこう言い放った。「本気の癖にいつまでたっても父さんから奪おうともしないでさ。ダラッダラ関係続けて妥協してる所がウザい。ママの事軽く見てんじゃないの」
娘の口から母の間男に「男気を見せて強奪しろ」とまで言われる父親が相当やばい奴なのかと言えばそうではない。ごく普通の温和なムーンキーパーの男だ。そう、ア・ムジも恋人の「夫」と面識があるし、なんなら交流すらある。妻と男の関係を知った上で。
ムーンキーパーは母親を中心にしたコミュニティだ。さらにミコッテという種族は男より女が圧倒的に多い。そういう事もあり恋人の生まれ育った地域では、男は複数の妻の家を渡り歩く「通い婚」が主流であり、女も形式的に夫を持つが別の男から子種を貰う事も少なくなかった。事実、ア・ムジはシオンの兄(つまり恋人の息子)とも面識があるが、黒い肌の妹とは似ても似着かない小麦色の肌で瞳孔は針のように細い、父であるサンシーカーの形質を受け継いだ青年だ。
そういった背景もあり、男の恋人は「奔放」であった。だが関係に線引きが無いわけではない。心に決めた伴侶がいて、後は皆等しく「恋人」なのである。ア・ムジは彼女ひとりを真剣に愛していたが、彼女にとっては何人かいる「恋人」のひとりであった。
「僕は正直……ムーンキーパーの文化は戸惑うことが多いけど……それを否定する事はしたくないんだ」
「……はぁ」
「それに何となく感覚は分かるしね。サンシーカーも男ひとりで複数の女性と関係を持つ文化だし」
「はぁ」
ア・ムジは丁寧に今の関係のまま維持したい理由を説明したつもりだったが、シオンは興味無さげに相槌を打っているだけであった。そして終いにはこう言い放ったのだった。
「要はなんだかんだ理由付けて尻込みしてるってわけね」
二の句が継げなかった。そう、文化がどうの彼女の意志がどうのと言葉を並べたが結局のところ夫から彼女の心を奪う気概が男には無かった。行動を起こして関係が終わってしまうのを恐れ、数いる「恋人」に甘んじている。それが現状。彼女が男を冷たくあしらっている理由がそこにあった。
***
そんな事を苦々しく思い出しながらア・ムジは白いクロスのかけられたダイニングテーブルに着席している。視線を上げると以前と同じ位置にキッチンがあり、シオンは彼に背を向けて何かしら飲食の準備をしていた。窓からロータノ海を一望できる明るくて清潔なキッチンだ。料理好きな彼女が自ら設えたそれらは、ここが彼女の住まいだった時から位置も設備も変えずそこにあった。譲り渡した後も時々訪れて、そこで母親のために腕を振るうためだろう。そこまで考えてア・ムジは笑みを漏らす。
「何ニヤニヤしてんの。気持ち悪」
ア・ムジは慌てて笑顔を引っ込めた。振り返ったシオンの手には品のいいティーカップと同じデザインのティーポットがあった。
無表情のまま、彼女はティーカップをア・ムジの前に置く。なんと叩きつけるようにはせずに、カップに似合った品の良い所作で! 口をあんぐり開けた男を後目に、シオンはそのカップに茶を注いだ。ふわりと紅茶の香りが漂う。香りだけでその辺りの市場では買えないものだと分かり、男は思わず口を開いた。
「これは、クルザス茶葉かな? かなり上級のものじゃないかい?」
「よくご存知で」
注ぎ終わると、シオンは棚から取り出したバーチシロップの瓶を傾け、紅茶の中に垂らした。なるほど、イシュガルドでは甘み付けのためにバーチシロップが用いられることがあるという。ア・ムジは正直甘い紅茶は好みではなかったが、――こうしたもてなしを恋人の娘から受けることが初めてだったもので――喜びの方が勝り、黙って受け入れる事にした。
「………………」
「………………」
いや待って。入れ過ぎじゃない?
声をかけようかと思う間に波々とシロップが注がれた。もはや紅茶とシロップの比率が逆転しそうである。
完全に静止するタイミングを逸してしまい、ア・ムジはハラハラとシオンの手元を見つめていた。そんな男の様子には目もくれず、シオンはシロップをそそぎ入れると、「どうぞ」と男に促す。
「……イタダキマス」
ア・ムジは怖々とカップを手に取ると、紅茶入りのバーチシロップと化したそれに口を付けた。分かってはいたが、シロップの味しかしない。
「………………」
「………………」
ちらりと伺い見ると、シオンも自らのカップに残りの茶を入れ、しかし自分は何も入れずにそれを口にしていた。なるほど、完全に嫌がらせてある。
しかし、とア・ムジは眉をひそめながら自らの紅茶(バーチシロップ)を啜り続ける。バーチシロップ自体も品質の良いもので口当たりが良い。紅茶と良いシロップと良い、良質な品を振る舞ってくれているという事は、少しは二人の仲が氷解しているという事の示唆なのではないか? …………
だめだ。急激に糖分を摂取して頭が回らなくなっているのかもしれない。
ぐるぐると考えを巡らせていると、コンコン、と扉がノックされた。素早く立ち上がって応対したのはシオンだった。
「ママ!? 今日来れないんじゃなかったの!?」
その言葉にア・ムジもびょんっと立ち上がった。ついでに尻尾も上向きに飛び跳ねる。
「え!? ニケさん!? だって今日……」
「ごめんなさいねぇ、グウェンさんが早く切り上げて帰りなさいって言うから」
そう言いながらダイニングスペースに姿を見せたのはア・ムジの愛しい恋人だ。しかし、男の顔は晴れない。それもそのはず、今まで会っていたグウェンとやらも、彼女の「恋人」のひとりであったからだ。
「えっ、すごい! 可愛いお部屋じゃない! シオンちゃんがしてくれたの?」
「え、……うん。そうだけど」
母親は直球で娘を褒め称えるが、娘の表情は硬い。シオンはむすっとしたまま目をそらすが、顔から照れと喜びが漏れ出ている。英雄だなんだと持て囃されてても、なんだかんだで年頃の娘さんなんだな、とア・ムジは少し頬を緩めた。
「ていうかママさぁ、今日ぐらいこいつの顔立ててやんなよ! よりによって別の男の所に行くぅ!?」
照れ隠しに飛ばされた母親への文句だが、突き刺さったのはア・ムジの胸の方へだった。
「だって、森を出るって言うならちゃんとしたお餞別を渡したいって」
「別の日でいいじゃん! もう今生会わないわけじゃないんでしょ?」
再び男の胸に言葉が突き刺さる。やっぱりそうなのか、とア・ムジは意気消沈した。
娘が母親にこのアパルトメントを譲り渡そうと決めた理由は2つあった。ひとつは単純に別の地に居を構えることになったから。もうひとつは、無事子どもたちを育て上げた母親が黒衣森での生活を畳み、森を出る事になったからだ。
そうして母親は移住先に伝手のある海都を選び、娘は新しく新居を探す手間を考えて居室を譲り渡す事にした。ア・ムジはたまたま海都で生活を営み、たまたま「恋人」だった事でその代理人の座に預かれた。ただそれだけなのだ。
ただ住処が変わるだけで今まで通り。黒衣森の夫に、海都の俺に、ウルダハにはまた別の男に変わらず逢いに行くのだろう。
「ムジくんもありがとう。助かったわ」
男の落胆を知ってか知らずか。ニケはにっこりと恋人に微笑んだ。
「いえ、なんのこれしき。他に困ったことがあったら何でも言ってください」
無理やり笑って、いつものように元気に返事をする。ア・ムジのそんな様子をシオンは薄目で睨んでいた。これもまたいつもの事だが……なんだか今日は視線が痛いな、とア・ムジは身にしみて感じた。
「ねぇシオンちゃん。他の部屋はどうなってるの?」
無邪気にはしゃぐ母親の声に気づき、シオンは表情を和らげた。
「あ、そうだった。ええとこっちが一応仕事スペース、作ったんだけど使う?」
「もちろん! 店は畳んだけど仕事は続けるもの。助かるわ」
「で、ここの扉から直接寝室なんだけど」
と、シオンがダイニングスペースの横にあった扉を開き、母親を招き入れる。しばらくして、わぁ! という歓声がダイニングスペースまで響いた。
「ムジくん! 見て!」
呼ばれてア・ムジも寝室に入り、唖然とした。
大きな窓から陽光が降り注ぐ寝室の中央に設えられたベッドは、想像していたものより大きいものだった。その上に添えられた可愛らしい桃色のクッションと落ち着いた青みのあるグレーのクッションが、二人で使う寝台であると主張している。それだけではない。片隅には、ささやかな作業机が備え付けられている。裁縫などの製作には狭いが、物を書いたり計算をするにはちょうど良いサイズだ。そして、ニケが自分で物書きをしたり算術をしたりなどという事はしない。必要な時は「恋人」であるア・ムジが担った。それはつまり。
「これ、「俺」の……?」
振り返ると、シオンが腕組みをして男を見上げていた。恐る恐る尋ねると、やはり素っ気ない返事が返ってきた。
「他に誰が使うのよ」
「…………」
……それは、ここで同棲をしても良いと、そういう事なのでしょうか?
余りに恐ろしくてア・ムジは問い直す事ができなかった。恋人の娘。年頃の少女。しかしそうではあるが彼女は、帝国兵を、凶悪な魔物を、果ては宇宙の果て?の何か良く分からない驚異を屠ってきた「英雄」なのである。間違いがあればその辺に転がっているミコッテ男ひとり造作もなく捻り潰されてしまう……!
「何、その怪物でも見る目は。やめてよね」
表情を読み取ったシオンは不愉快そうに顔を歪ませた。
「いや、ごめん。そんなつもりじゃ」
「必要だと思ったから作った。それだけだから」
そう言うとシオンは改めてア・ムジを睨みつけた。「腹ァくくれっつってんのよ」
「は……」
ア・ムジの返答を待たず、シオンは懐に閉まっていた部屋の鍵を母親に手渡した。そして、男にも同じものを手渡す。
「じゃ、そういうことだから」
「まぁまぁまぁ! これからよろしく、って事でいいのかしら? ムジくん」
「え、は……?」
ア・ムジは目を白黒させている。
「ニケさんは、そのつもりだったんですか!?」
「そのつもり、とは違うけど、ぜひそうしたいわ! でも貴方がどうしたいか聞いてからじゃないと」
ニケはにこにこと男を見上げて言った。「それで、どうかしら? 一緒に住むのは嫌?」
「そんな! 願ってもないことです!」
けど、ご主人はなんか言わないんですか。言い訳がましくモゴモゴと口ごもるア・ムジを一瞥して、シオンはため息をついた。
「はぁ、お前から切り出せよ。かっこ悪」
「シオンちゃん! だめよ。そんな意地悪な事言ったら」
ニケはふくれっ面の娘を苦笑いして窘めた。「ムジくんにも事情があるんだから」
「ふうん……? あんの? 事情」
腕を組んで酷薄に微笑む恋人の娘を前に、男は首を振るしか無かった。
「ありません」
「そう」
その言葉を聞いて腹に落ちたらしく、シオンは表情を緩めた。わざとらしく肩を竦めると、「じゃ、帰るわ」と切り出す。
「え、もう帰るの? ママにも紅茶淹れてほしかったのに!」
どうやらさり気なくダイニングテーブルの上を見ていたらしい。母親のおねだりをシオンははねつけた。
「ママが飲みたいのはイシュガルドティーでしょ? 今日はヤクの乳持ってきてないもん。また今度ね」
***
アパルトメントのロビーまでシオンを見送りに出たア・ムジは礼を言うべきか謝罪するべきか考えあぐねていた。アシストしてくれた礼を言えば「自分でやれよ軟弱」と罵られそうだし、彼女の父親を差し置いてしまった事を謝罪すれば「謝る相手が違うだろ馬鹿」と罵られそうである。……なんにせよどう罵られるかの違いしかない。
見送りに来た割に何も言わない(何かを言いたそうにしてはいるが)母親の恋人に、シオンは大きくため息をついた。
「本当に、同じサンシーカーかこいつ」
誰と比べられたのか分からないが、恐らく彼女の同僚、というか仲間と言ったほうが良いだろうか。ともかくあの面子であろう。英雄に負けじと強く、賢く、そして一緒に宇宙の果てまで行くような連中と比べないでほしい。
シオンは振り返ると、ア・ムジに言う。
「父さんは他の奥さんもいたから。ママと一緒に住んだりはしなかったし、ママも一緒に住みたいなんて事言わなかった」
首をかしげるア・ムジに、さらに続ける「お前はママが望んで、一緒に住む事になる。それがどういう意味かよく考えると良いよ」
「……え」
「良かったなツキがまわってきて」
本当にこいつのどこが良かったんだ、とぼやくシオンを唖然とした顔でア・ムジは見下ろした。
「え、え、え」
「だから腹ァくくれっつってんのよ。はぁ」
また大きくため息をつかれる。「まぁ、いいや。ママの事はよろしくね。たまに遊びに行くけど、その時は遠慮してよね」
じゃ、と背を向けて恋人の娘は去っていく。投げかけられた言葉を反芻しながら、男は呆然とその背中に手を振るのだった。