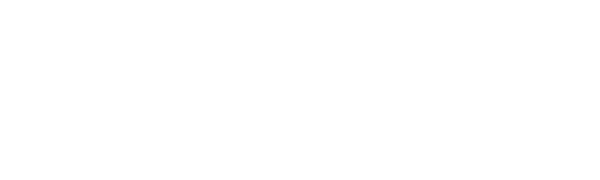掌編:南部森林・猟師の述懐
南部森林在住のお兄さんの日記のようなもの。自機は出ない。コーヒークッキーは出る。
南部森林の外れに、俺が毎日立ち寄る店がある。そこは小さな雑貨屋だが店主の女が食料品や酒も取り扱っていて、店の片隅には買ったものを飲食できるスペースがあった。俺はそこで仕事終わりに酒と煙草を買い、その場で一杯引っ掛けるのが日課だった。
今日もそうしてテーブル席で酒を煽っている。カウンター席では、常連の親父が女将と大声で談笑していた。あの親父は俺が来るときに毎回いるわけではないが、今日はいる。店内に入ってこの親父がカウンターに陣取っているのを見ると「ああ今日は運が悪い」と思う程度の遭遇率。そして今日は運の悪い日という事だ。
「……そうだそうだ。ガキの頃の嬢ちゃんが焼いたクッキーなんか、そら酷いもんだった! あんまりバッサバサで口の中の水分が全部吸い取られる勢いだったもんなあ!」
どうやら今日は女将の娘の話をしているらしい。その娘は長じて冒険者になった、と以前女将と親父が話し込んでいたが(というより親父の声が大きすぎて話の内容が筒抜けだ)、今日はその娘の昔話に花を咲かせているらしい。
「うふふ、そんなこともあったわねえ! ごめんなさいねその時は」
「いいんだよ子供の作ったもんなんだから。でもバッサバサのクッキー焼いてたあの嬢ちゃんが、ねえ! あんな美味い菓子作るようになってさ。特にこないだの、コーヒー豆が入ったやつなんか最高だったな!」
「あら、ちょうどいくつかあるわよ。この間送ってきてくれたの」
「そりゃあいい! 10枚くらい包んでくれよ! 娘とそいつの友達がまたあれ食べたいってしょっちゅう言うんだよ」
少しやかましいな、と顔をしかめてシードルの入った瓶の口を舐めていると、貴方もおひとついかが、と女将さんが例のクッキーをひとつ懐紙に載せて俺のテーブルに置いた。甘いものは得意ではないし、そもそも酒の肴には場違いすぎる。しかし、無禄ににもできず俺は愛想笑いを浮かべて礼を述べる事にした。