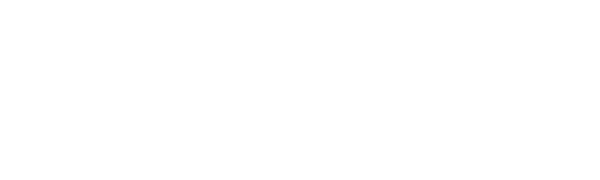エンピレアムの怪
お家買ったヒカセンのリテイナーが某象と邂逅する話
・自機(女)は出ない。リテイナーは出る。
・暁月(6.0)後の描写がある
山の国に新しく作られたその街は高台に位置している。その街中には東西に高低差があり、西側の高台から全体を一望することができる。逆に東の広場から街の外を望めば、下に壮麗なクルザスの山々がそびえている。家々を繫ぐ通りに敷き詰められた重厚な石畳にはその日、この国では珍しい暖かな陽光が降り注いでいた。
イシュガルドに新しく作られた冒険者居住区「エンピレアム」はその名の通り天高くにある石造りの空中都市のようだ。その一角、小さな家の前に、めいめいに荷物を抱えた三人の男女が集っていた。
「一番地価が低い、小さい家だって話だったけど、なかなか悪くないわね」
「庭もありますしね」
「そらアパルトメントと比べたらそーだろうよ」
口々に家の感想を述べる彼らは、この冒険者居住区に新たに居を構える者……かの「暁の英雄」に雇われているリテイナー達だった。しかしその場に当の本人の姿はない。相変わらず頼まれごとやらお使いやらに駆り出され、到着が遅れているためだ。
「いやでもよ、一応あんなだが星を救った英雄サマだぜ?」
そのうちの一人、一番背の高いアウラ族の男が不満げに口を開いた「それが特に特徴もねぇ五等地の小せえ区画ってどうなんだ?普通一等地の広い屋敷じゃねえの?」
その言葉を合図に一同はエンピレアムの奥、高台に鎮座する一番大きな屋敷を仰ぐ。そこには最近流行りらしいお菓子の家がでんと鎮座していた。最も目立つ一等地にそびえ立つそれは艶やかな赤い屋根と眩いばかりの黄金色の壁。是非はともかく、この区画に入って一番に目に飛び込んでくる屋敷だった。
「……星を救おうが国を救おうが金が無きゃLサイズなんて買えないわよ」
目を細めてその色鮮やかな屋敷を見上げながら、ミコッテ族の女が口をひらいた。「そもそもあの子がここを選んでここに応募したのよ? 雇い主が決めたんだから私達は文句言わずハイっつっときゃいいのよ」
「いや上の連中が斡旋してくれたりしねぇの?っていう疑問なんだって」
「そう言えばそうッスよね。ご主人ってこの国にもデカい貸しあるっすよね?」
「あの子がそういうのを良しとすると思う?とっくの前に固辞してるわよ」
この話は終わりとばかりに、一番古株の女リテイナーはパンパンと手を叩いた。「ほら、さっさと荷解きするわよ。口より手を動かして頂戴」
***
いち冒険者時代から、かの英雄にはささやかな目標があった。すなわち、冒険者居住区に立派な家を建て、そこに住まう事である。多くの冒険者にとって、各国に用意された「冒険者居住区」に居を構えることは大きな目標、または憧れであった。
だが実際問題、各国の用意できる土地は限られている。その限られた土地に多くの居住希望者が殺到するゆえ、もはや遠い目標、果てなき憧れと言っても過言ではない状況だった。そんな事もあり、多くの冒険者がそうするように英雄もまた、リムサ・ロミンサのアパルトメントに身を寄せつつ半ば叶わぬ夢と嘯いてすらいた。
そんな中、かの英雄と縁深い国イシュガルドもまた、冒険者居住区(エンピレアム)を開くことを発表した。加えて、従来先着方式だった土地販売を抽選方式にするという発表。それを聞いた英雄も(数日逡巡したのち)、ようやく手を上げたのだった。
「いやーでも、結果的に当たって良かったっすよねぇ」
自らが作ったサンドイッチを頬張りながら、ヴィエラ族の青年は傍らに座る同僚に笑いかけた。その同僚、アウラ族の男もまたもそもそとサンドイッチを咀嚼している。少人数で生活する程度の小さな家である。早々に荷解きを終え、なんなら家の中の調度品も設置し終わり、リテイナー達は新居の庭で長い昼食休憩をとっていた。
「抽選結果通達の行違いでトラブった時はマジで生きた心地しなかったっすよ」
「まぁ、他の国でもやってなかった初めての試みって奴だからね。そういうこともあるでしょう」
男たちとは違い、ミコッテ族の女は庭に新しく植木を植えたり剪定したりと忙しい。新居の庭の手入れ役は、園芸師である彼女に自然と任されたようだ。
「でもそのせいで自分の入居もままならん結果になったわけだろ。不憫だよなぁ「英雄サマ」も」
アウラ族の男が大げさに肩をすくめて見せる。事実、結果の通達トラブルで予定より遅れた当選を見届けた「英雄サマ」は喜びに浸る暇すらなく、当選に半信半疑の顔で家屋を建てる手続きだけすませると、緊急で入った依頼のために慌てて出立していったのだった。彼女のリテイナー達にすべてを任せて。
「こんな状態でゆっくりする時間なんてあるのか? この家で」
「あら。私はゆくゆく冒険者のご友人を招いて二人でここを使うって聞いたけれど」
「あ!? 初耳だぞそれ」
「貴方はベンチャーで出払ってたものね」
憤慨にも近い驚きの顔を見せるアウラ族の男には目も向けず、庭木の剪定をしながらミコッテ族の女は淡々と答える。
「あ、もしかしてちょっと前にリムサのアパルトメントで会った!?あのララフェルの女の子ッスかね……」
そう言って先輩の方を向いたヴィエラ族の青年は、彼女が唖然とした顔で剪定の手を止めているさまに気づき、追って視線の先を追った。
「……象だ」
果たして。
新居の前、ちょうどサインボードの目の前にそれはいた。冴え渡るような蒼い色をした象が腰に手をあて、リテイナー達に視線を向けるようにして立っていた。
***
「象だ」
「象ッスね」
「……幻覚じゃないみたいね」
三人は唖然とした顔でしばしその蒼い象と見つめ合った。いや、そうする他ないだろう。それ以外どうしろというのだ。
ふと、ヴィエラ族の青年が口を開く。
「なんか……睨まれてないッスか? 俺たち」
は?と先輩リテイナー二人は新人の青年に顔を向ける。睨まれるも何も、蒼い象は表情も変えずつぶらな瞳をこちらに向けているだけだ。だって、着ぐるみだし!
「ふ……フフフフフフ!フ・マユさん!絶対睨んでる!!睨んでるっす!!!」
「そんなわけないでしょ。大体私達睨まれるようなことしてないじゃないの」
呆れ顔で返すが哀れにもこのヴィエラ青年は完全にパニックになっている。女は大きくため息をついた。ほんっとうに!この後輩は!!意気地がない!!
一方、もうひとりの後輩たるアウラ族の男は腕組みをし、象と睨み合い(?)ながら何か考えているようだった。いや、何かを思い出そうとしているような……
「あ」
思い出したらしい。「そういえばリテイナー仲間が言ってたな。……エンピレアムには会うと幸運が訪れるとかいう……象、が時折出没するとかなんとか」
何だそれは。女は尖った耳をペタンと伏せ、眉間を抑えて天を仰いだ。
彼女らの雇い主達、すなわち冒険者達は時折そういった胡乱な噂を持ち込んで来る。市街に現れる幽霊。とある遺跡の防衛機構に潜む猫。あるいはどこからともなく現れる謎のビーバー。だがそれらの殆どがまことしやかに語られる嘘だ。
だから、またその手の奴だと思って聞き流して忘れてたんだよ!! 本当だと思わねーじゃねえか!! アウラ族の男ががなり立てる声を、ミコッテ族の女は遠のきそうな意識で聞いていた。
「そう言うことなら」
ふと。少し落ち着きを取り戻したヴィエラ族の青年がおずおずと切り出した。「自己紹介とか、したほうが良くないッスか???」
何が????「そう言うことなら」なの???????
先輩二人はわけがわからないと顔を見合わせ、もう一度象に目を向けた。いつの間にか腰にあてていた手は組まれ、何か考え込むような……そんなポーズになっている。
「………………」
「………………」
二人の沈黙をゴーサインと捉えたか。ヴィエラ族の青年は一歩前に出、すう、と息を吸った。
「あっ、あのっ!これからお世話になります!!俺達シオンさんに雇ってもらってるリテイナーで!!」
先輩たちが静止する間もなく、青年は早口でまくし立てた。「えーと、シオン……シオン・フレッカです!暁の血盟の!!俺達は彼女のリテイナーで、俺はアレン・ヘルグランといいます!こちらの女性がフ・マユ・クノ、こちらの男性はタドヴァン・イルマズです」
「それは本名でリテイナー名じゃねえよ……」
もはや諦め顔でアウラ族の男がぼやく。かくいう女の方も氏族名と姓まではリテイナー名に登録していないのだが、……いやもうそんな些末な事はどうでも良いな、と再び天を仰いだ。
「………………」
しばしなんとも言えない沈黙が流れる。が。
「!」
蒼い象は合点がいったかのように腕組みをしてうなずいた。そして、丁寧にお辞儀をひとつしてみせた。
(エレゼンの礼だわ……)
(エレゼンの礼の仕方ッスね……)
(まあ……ここイシュガルドだもんな)
三者三様、ぼんやりとそう考えながら礼を受け取ると、そのまま踵を返して去っていく蒼い象を見送ったのだった。
***
「……なぁ」
もはや遠くなった青い影を腕を組んで眺めながら、アウラ族の男、タドヴァンは口を開いた。
「これもふと思い出した話なんだが……なぁ、いいか?…………暁にはイシュガルドの蒼天騎士団総長と仲の良い、元蒼の竜騎士がいるだろう?」
ミコッテ族の女もとい、フ・マユは顔を歪ませた。それ以上ややこしい情報を入れてくれるなという表情だ。しかし、特に男の話を遮る事はしなかった。する気力さえなかった、というのが本当だ。
「シオンが彼に直接聞いたそうだが……暁が解散する事になって、その竜騎士は総長にここの警備に就くよう勧誘されたんだそうだ。だがそれを断ったと。でだ」
代わりにこれを着てエンピレアムの人気者になれよ、とかの総長に象の着ぐるみを送ったらしいぞ。
フ・マユは今日三度目の……耳をべったりと伏せ、眉間をつまみ、天を仰いだ。手にしていたサイズも手からすり抜け落ちそうだった。
「それは……流石に嘘でしょう。嘘であって。本当に」
彼女の主人は多少冒険者らしい茶目っ気はあるが基本的に真面目な性格だ。先に挙げたような胡乱な噂も滅多には口にしない。そんな彼女がそう語ったのなら、事実なのだろう。かの竜騎士が実質この国のトップの勧誘を固辞した事も。……象の着ぐるみを送った事も。
だが、流石に、その事実から蒼い象がエンピレアムを闊歩している事象には繋がらない。親友の冗談(それとも皮肉か?)を素直に受け取って国の実質トップが「幸運を呼ぶ象」になるとか、そんな事あってたまるか…………!
同じことを思ったらしいタドヴァンも額に手を当ててうなだれていた。
「俺もそうだと思う。そうあってくれ。本当に」
「……あの、でも」
同じように青い影を見送っていたヴィエラ族の男、アレンはおずおずと先輩リテイナー達へ視線を向けた。信じられないものを見たような顔をして。
「あの象が腰に下げてた青い剣、俺見覚えがあるんスけど……」
『見ていない!!』 「俺は」「私は」 『何も、見ていない!!』
その叫びは図らずも。
彼女たちの雇い主が、かつて訪れた始まりの地で触れたやり取りに通じるものがあったのだが、それを知る由はもちろん無い。